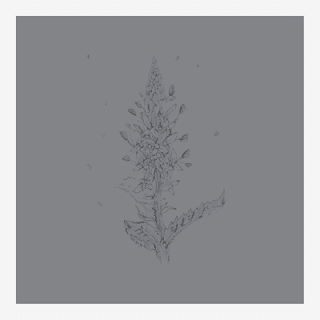6月のリスニングから
...
Sakanoshita Norimasa - Toshi No Mezame (Weiss, 2016)
異種混合のセッションで様々なプレーヤー達と交流し、ソロでは、ギャラリーや書店など人と人が交差する空間での演奏活動を行っている東京在住のギタリスト/作曲家=坂ノ下典正。スペインの作曲家Francisco Tárrega(フランシスコ・タレガ)やAndrés Segovia(アンドレス・セゴビア)の楽曲を出発点としながらも、クラシックやジャズ、ブラジル音楽などのエッセンスを織り交ぜたインストゥルメンタル作品を発表している。「都市の目覚め」は、クラシカル・ギターとエレクトリック・ギターを奏した最新作。8曲のうち3曲がスタジオ録音、5曲が伊豆の国市にあるギャラリーnoir/NOKTAで行われたライブ・パフォーマンスで、特にライブ音源を聴いていると、瞬間的に湧いてくるリズム、アレンジ、曲中の呼吸、室内で人が動く気配や少しの躓きも泰然と受け入れ、完全であることから一歩引いたところに自由さを求める姿勢が、このギタリスト特有の打ち解けた空気や心地よいバランス感に繋がってゆくように感じられる。ブダペスト出身の現代美術作家Richard Weiss(リチャード・ヴァイス)が立ち上げたレーベルWeissの第2弾タイトルとして今春にリリース。
Conrad Setó – Joc De Dames (Audiovisuals De Sarrià, 1986/2016)
初作「Magic」を超える傑作。4月からデジタル・フォーマットで配信されはじめ、念願かなってダブルアルバムの全てを聴くことができた。Conrad Setó(コンラッド・セト)は、スペイン国内でも独自の文化を持つカタルーニャ州のタラゴナ県モンブラン出身のピアニスト。76年に室内楽グループTanitを結成し、民主化により音楽市場が開放された70年代後期以降は新たな音楽シーンを先導した。「Joc De Dames」はカタルーニャ文化圏の伝統音楽や現代音楽を扱うバルセロナのレーベルから86年にリリースしたソロ2作目。身近な老婦方に捧げたアルバムだろうか、ベッツィやシルヴィ、アレハンドラという曲名は女性の名前で、タイトルは「婦人達の遊び」と訳せる。互いの作品を支えあう盟友ギタリストAlbert Giménez(アルベルト・ヒメネス)をはじめ、ベーシストEduard Altaba(エドアルド・アルタバ)、打楽器奏者Angel Pereira(アンヘル・ペレイラ)といったカタラン・ジャズロック最前衛の面々が参加し、Giménezのソロ作にも通じるフォークロアの情調に、近代音楽や電子音楽の要素を折衷したコンテンポラリー・ジャズを全編にわたって展開している。自治政府によるベストアルバム賞の第一回受賞作。
Erik Wøllo - Where It All Begins
(LP: Hot Club Records, 1983 / CD: Monumental Records,1999)
北欧のニューエイジ・ミュージック界を代表するノルウェイの作曲家/ギタリストErik Wøllo(エリック・ウォロ)。10代の頃にイギリスのプログレッシヴ・ロックに多大な影響を受け、ドビュッシーやサティなどクラシック音楽の技法を身につけた。電子楽器を使った新しいアプローチを模索するため、84年にスタジオ=ウィンターガーデンを構え、シンセサイザーやシーケンサーで絵を描くように作り上げた85年作「Traces」で、ソロ・アーティストとしての方向性を確立。自然の神秘、感情と風景、汎地球的な民族幻想をモチーフに、現在まで数多くのソロ作品をリリースし、映画・演劇・バレエなどの音楽も手掛けている。「Where It All Begins」は、ニューエイジ・エレクトロニクス路線に転向する以前、83年にリリースされた初のリーダー作で、Terje Rypdal(テリエ・リピダル)の継承者とも称されるWølloのウェットなギターと、Brynjar Hoff(ブリニャル・ホフ)のオーボエをフィーチャーし、冷たい水の底で揺れる蒼い炎をイメージさせる幽寂としたコンテンポラリー・ジャズ寄りのサウンドに仕上げられている。本編はもとより、CD化に際して追加された "Searching For Hidden Pictures"(84年のアルバム「Dreams Of Pyramids」に収録、現在は廃盤)が殊に素晴らしい。ECMとジャーマン・エレクトロニクスを結ぶ、21分にも及ぶ3部構成のミニマリスティックな組曲は、その後の作風を左右する大きな手がかりになったのかもしれない。
Kenichi Kanazawa - To Strike the Iron: Fragments of Sounds (NAF, 2000)
-
「松本一哉『水のかたち』リリースツアー」の新潟公演で、第二部に行ったレコードリスニング会のために用意した資料の一つ。その日のライブは、波紋音や三昧琴といった鉄製音具など打楽器によるパフォーマンスで、楽器一式の中には「音のかけら」という音具のミニサイズが含まれていた。「音のかけら」は、円形の鉄板をパズルのように不規則な形に熔断し、大小様々な形状の欠片に触れることで、それぞれが持つ固有の響きを発見してゆく、彫刻家=金沢健一による視覚・聴覚の作品。このCD付きカタログは、2000年8月から10月にかけて新津市美術館(現・新潟市新津美術館)で開催された「共鳴する空間 金沢健一 音のかけら展」に際して出版されたもので、同年7月から現地滞在しながら制作した直径1.5mの鉄板による5枚の連作など展示の解説が掲載され、CDには、会期中に行われた金沢氏本人とパーカッショニスト永田砂知子によるサウンド・パフォーマンスの模様が収録されている。作者ゆかりの作家として環境音楽家=吉村弘が文章を寄せているが、吉村弘が87年に企画・プロデュースしたサウンドアート展「サウンド・ガーデン」(ストライプ美術館)への参加が、「音のかけら」制作の第一歩になったという。
Ashberry - In Music We Are Still Together: The 'R' Trilogy (Wylfen Editions, 2014)
夢の断片を縫い繕った淡く霞んだ音像に、土や草の匂いや手触りを感じさせるアンビエント・フォーク作。作者はトルコ・アンカラを拠点に活動するAshberry(アシュベリー)ことAtay İlgün(アタイ・イレグン)。Wounded Wolf Pressというレーベルを運営し、詩・短編小説・写真・フォークロアにフォーカスした手製のチャップブックやCD/レコードを出版している。今年3月、既作EP「'R' 3部作」を中心とする「In Music We Are Still Together」が、新たに2つの異なる仕様でリリースされた。5種類の混抄紙を使った美しいハードカバー・スリーヴのアート・エディションには、同レーベルアーティストによるリミックスやアウトテイクを含む3枚のCDに加え、詩のカード、冊子、メグサハッカやマウンテンタイムなどドライハーブが入った小瓶がパッケージされている。元々、レーベル立ち上げのきっかけとなった「'R' 3部作」は、屋根裏のアトリエと庭を行き来しながら即興的に作られ、古くから家に眠る楽器へのオマージュが込められているという。このグレーのカバーは、2つのEPをまとめたWylfen Editionsのデジタル・エディション。3年前のインタビューでは、トルコのギタリストErkan Oğur(エルカン・オグル)や吟遊詩人Asik Veysel(アシュク・ヴェイセル)を好きな音楽家に挙げている。▲
Wolf Müller - The Ransom Note Mix
International Feelのミニアルバム・シリーズからCassとのコラボレーション作「The Sound Of Glades」をリリースした、デュッセルドルフのDJ/プロデューサーWolf Muller aka Jan Schulte(ヴォルフ・ミュラー/ヤン・シュルテ)。UK拠点のウェブメディアThe Ransom Noteに提供したゲストミックス。